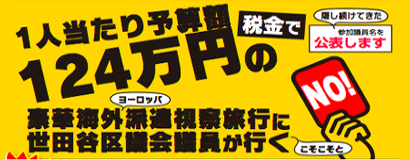令和2年12月16日(水) 午後3時
1.報告事項
(1)事務事業見直しの状況について(追加報告)
(2)ICTを活用した新たな学びの推進状況について
(3)新BOP学童クラブの実施時間延長モデル事業の延長について
(4)電気設備改修工事に伴う「世田谷区立郷土資料館臨時休館」について
(5)区立図書館運営体制あり方検討委員会における検討状況について
(6)世田谷図書館及び梅丘図書館の運営事業者選定結果について
(7)新型コロナウイルス感染症に係る教育委員会事務局の対応について(その7)
(8)その他
2.協議事項
(1)次回委員会の開催について
平塚敬二 委員長
本日は報告事項の聴取等を行います。
まず、委員会運営に関しましては、引き続き、新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をお願いいたします。
なお、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクを御使用いただきますようお願いいたします。
それでは、1報告事項に入ります。
(1)事務事業見直しの状況について(追加報告)について、理事者の説明を願います。
會田 教育総務課長
それでは、事務事業見直しの状況について(追加報告)につきまして御説明いたします。
なお、本件は五常任委員会の併せ報告でございます。
1の趣旨でございます。十一月十日、十一日に開催されました各常任委員会におきまして、令和三年度予算編成における事務事業見直しの途中経過を報告いたしました。今回、追加の見直し検討項目や見直し検討項目についての内容を取りまとめましたので、追加という形で御報告させていただくものです。
2の見直し状況でございます。(1)現時点の見直し効果額についてです。令和三年度予算編成を進めるに当たり、各部において事業の在り方や方向性を一つ一つ検証し、ゼロベースで所要経費を見積もってまいったところです。なお、現在、予算編成過程において、ここに掲載の項目も含め見直し内容や金額の整理、調整の途中段階で、随時数字が増減している状況であり、作業を中断して集計することは困難という判断をいたしまして、ここでは前回の報告時と同様に、各部による予算見積り時点での見直し効果額の集計として記載しております。
(2)主な見直し検討項目についてです。今回、主な見直し検討項目として、十一月の報告時から二点、新たな内容を追加しております。
一点目が主な見直し検討項目の追加です。そして、二点目が主な見直し検討項目についての詳細内容の追加でございます。こちらにつきましては別紙となっておりまして、別紙の七ページ、こちらが教育委員会領域の該当部分でございますので、七ページのほうを御覧いただけますでしょうか。
こちらの表で、左端に見直しの効果額の合計、中央に主な見直し検討項目、そしてその内容、右側のほうに参りまして見直しの効果額、そして右側で見直しの区分と見直しの視点という形で二段書きで掲載しているところです。見直しの区分につきましては、ページの下部の左側の表にありますように、見直しの内容や方向性をア、イ、ウ、エという形の記号で表し、掲載しております。見直しの視点のほうでございますが、こちらにつきましては、各事業の点検検証に当たって、見直しの方向性に至った要因を、こちらはA、B、C、D、Eという五つの見直しの視点で分類しております。
なお、一番下のほうでございますが、主な見直し検討項目のうち、欄外に米印のついた事業が今回新たに掲載した見直し項目です。また、同じく欄外に黒ダイヤの印のついた事業につきましては、今年度当初に事務事業の緊急見直しを行った事業の見直し対応の継続です。
ちなみに、新規に掲載した項目につきましての記載といたしましては、中ほどの小中学生海外派遣事業の休止、そしてアドベンチャーin多摩川の開催休止、そして、その他、電算経費等内部事務、事業費の精算につきましては、八十五予算事業をまとめてという形の金額で掲載させていただいております。
かがみ文の裏面のほうにお戻りいただけますでしょうか。今後でございますが、今後、予算案の編成過程において、見直し検討項目についての内容や金額の整理、調整、その他事業の一時休止、公共施設やインフラの工事時期の調整、内部経費の一層の縮減等によるさらなる見直しを進めて、収支均衡した予算案の編成に努めてまいります。
4として、今後のスケジュールについてです。今後、予算編成と同時進行で事務事業見直しについて調整を進めてまいります。その結果といたしまして、令和三年二月の常任委員会におきまして、事務事業見直しの結果報告を報告させていただく予定でございます。
説明は以上でございます。
平塚敬二 委員長
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
あべ力也 委員
様々な事業がコロナ禍ということで、教育委員会のほうで御配慮をいただいて、中止をする事業もあるし、見直しをするということで、何につけ子どもたちの安全とか命を守るということが最優先でしょうから、こういう結論になったということも仕方がないことだと思いますけれども、例えば縮小して移動教室をやる場合でも、一泊二日ということでも、その感染のリスクであったり、そういうことは払拭はできないわけですけれども、仮に参加をされた児童生徒さんの中にコロナなり何なり発症したというようなことがあった場合には、例えば参加をされた生徒さんと濃厚接触にあった児童とか、そういう方というのは、学校には出てこられない、隔離の状態になるわけですから、当然、学級が閉鎖をされたり、学校が閉鎖をされたりというようなことに発展するということになると思うんです。そういうことをいろいろ懸念をされて、二泊ということではなくて、なるべく危険を少なくするということで一泊二日ということにされたんだと思いますけれども、参加をされた児童生徒の中に、そういうコロナに発症したという場合には、先ほど申し上げたように、学級閉鎖であったり、学校閉鎖というようなことも行われるというふうに認識しておいてよろしいんでしょうか。
淺野 教育総務部長
お話しのとおり、この間、学校で、この後でまた御報告等ありますけれども、保健所と一緒に濃厚接触者を確定して、どういう範囲の方が待機されるか、そういった形で確定しております。ですから、場所がどこであったとしても、学校行事でそういったような形で、仮にですが、コロナの陽性者が出た場合には、同じように対応してまいります。
あべ力也 委員
学校行事を継続するということも大事だと思いますし、このコロナ禍においてコロナの発症とか、そういうリスクに対して教育委員会としてしっかり対応するということも必要だと思います。今回のこの事務事業の見直しに当たって、いろんな考えがあって、教育委員会としても様々検討された結果だと思いますので、とにかくコロナの収束がまだはっきりしない、ワクチンの接種についても、他の国では始まっていますけれども、日本のワクチンの認可の在り方なんかで言えば、まだちょっと時間がかかるのかなというふうに思っておりますので、いずれにしても学校の安全とか児童生徒さんの安全を最優先に、ぜひ検討していただきたいということを要望しておきたいと思います。
平塚敬二 委員長
それでは、(2)ICTを活用した新たな学びの推進状況について、理事者の説明を願います。
會田 教育総務課長
それでは、ICTを活用した新たな学びの推進状況について御報告をさせていただきます。
ICT関連につきましては、十一月十日、あるいは九月、七月とタイミングによって推進状況を御報告させていただきましたが、今回につきましては、大きく三点について御報告させていただきます。
2児童・生徒用タブレット型情報端末の配備についてです。こちらにつきましては、第一次配備ということで約一万台というお話を報告してまいりました。こちらにつきまして、十一月十六日から十一月三十日の期間で、中学三年生、それから小学六年生を対象とした約一万台の配備を実施したところでございます。
(2)として、第二次配備、残りの約三万三千台でございますが、こちらにつきましては、考え方として、まず中学校の中学一年、二年を対象に配備を行い、その後、小学校六十一校への配備をなるべく早く行っていきたいというふうに考えてございます。
3ソフトウェアの選定・活用についてです。こちらにつきましては、令和三年度に使用する学習支援ソフト、ドリル系ソフト、動画配信系ソフトについて、プロポーザルで選んでまいりますという報告を今までさせていただきました。
具体的に今の状況でございますが、(1)学習支援ソフトウェア及びドリル系ソフトウェアにつきましては、補正予算のほうも議決いただきましたが、令和三年度に使用する学習支援ソフトウエア及びドリル系ソフトウエア選定について、十一月二十日に公告ということを開始し、公募によるプロポーザル方式の選定を実施中です。こちらにつきましては、まずは、どのソフトにするかということを公募により選定いたしまして、その後、入札等によって具体的に落札してまいりたいというような形を取りたいというふうに今考えているところです。
(2)動画配信系ソフトウェアにつきましては、ズームのライセンスにつきまして購入をさせていただきましたので、こちらにつきましては、今年度ではなく来年度に今後のソフトウエアをどうするかということは、選定のほうを考えてまいりたいと考えております。
4の学校緊急連絡情報発信サービスシステムです。こちらにつきましては、いわゆる緊急情報メールの後継といいますか、また、よりこちらにありますような区立小中学校・幼稚園、教育委員会事務局から、緊急連絡等の情報配信、さらには、その既読確認や保護者からの欠席連絡等の機能も兼ね備えた双方向型にしていくというところで、そういったシステムというところで今までお話しさせていただきましたが、委託先の業者を選定いたしましたので、それとその内容についてです。
委託先業者ですが、プロポーザルを実施いたしまして、六社が参加いたしました。こちらにつきまして、バイザー株式会社を選定事業者として選定いたしました。裏面に参りまして、履行期間、契約予定金額は記載のとおりです。令和二年度としての金額、③ですが、令和三年度からの運用経費については予算計上しているところですので、記載としては、令和二年度分だけここには記載させていただいております。
(2)として、システムの主な機能ということで、緊急情報連絡の配信機能につきましては、今までのメール機能に加えてといいますか、スマートフォンやタブレット端末、携帯電話、様々な機器に対して、きちんと緊急連絡等の情報を配信する機能を有するということ。それから、こちらにつきまして、②の既読確認機能ですが、学校から発信した情報につきまして、保護者が既読しているかどうかの確認ができる機能というところ、また、いわゆるプッシュ通知機能、スマホで言いますとポップアップとかバイブのような機能でありますとか、情報を未確認の保護者には再通知を行うというような機能を持っておりますので、より確実に通知のほうをしてまいりたいと考えてございます。また、③欠席連絡機能でございますが、こちらにつきましては、スマートフォン等で利用できるアプリケーションとなりますので、日付、欠席理由等を入力して、学校に欠席連絡を送信できるということがこれによって実現することができます。
(3)今後のスケジュール(予定)でございますが、十二月から二月にかけて、システムの設定や様々な登録、テスト、そして研修といったことを実施してまいりたいと思っています。三月から現行の緊急情報メールのシステムがありますので、並行運用という形で行いまして、四月から新システムにきちんと切り替えて、新システムの本格運用ということで考えているところでございます。
説明は以上でございます。
平塚敬二 委員長
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
あべ力也 委員
タブレットの一次配備、二次配備ということの御報告でありますけれども、萩生田文科大臣も、令和三年度がICTの元年だということで言われていますし、国が実質的な予算をつけて、タブレットを児童生徒にということですから、これは世田谷だけの事業ではなくて、日本の国全体として、タブレットを活用したICT教育ということに踏み出すというのが来年度ということなんでしょう。
それで、配付をして、その準備を進めながら、またソフトとか、そういうことも整えていくということなんだと思いますけれども、ちょっと配付の時期が、体制を整える前に配付をされたのかなというふうに私は感じるんですが、いずれにしても、児童生徒に対する説明と親御さんに対しても説明ということをして、本格実施に向けて様々準備をしていただきたいと思うんですけれども、そういう認識でよろしいんですか。簡単に回答いただければと思いますけれども。
會田 教育総務課長
今、委員お話しのとおり、まず端末の配備でありますとかネットワークの整備、またアプリケーションの何を選んでいくかの選定、そういったものは本当に準備だと思っています。それによって、終わるんじゃなくて始まりというところで、令和三年度が元年ということは、そのとおりかなというふうに感じております。
あべ力也 委員
初めての配備ということが、世田谷をはじめ、公立の小中学校で実施をされるという中で、いろいろ環境も変わっていく中で、教育委員会のほうが学校や児童生徒、そして親御さんにしっかりとした説明で、何か疑問になる点がなるべく払拭されるような説明をしっかりしていただければなというふうに思います。本格実施に向けて様々準備も大変だと思いますけれども、しっかり取り組んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
あべ力也 委員
こうしたICTであるとか、デジタル化ということの最大のメリットというのは、マクロ的にいろんなことができるということだと思うんですね。それで、もちろん教育委員会というのは各自治体ごとにあって、その独自性であったり、独立性とかということが担保されて、独自の教育をするということも大事なことだと思うんですけれども、そのデジタル化の最大のメリットを生かすために、文科省としては、例えばタブレットに統一のアプリケーション、全国一律のアプリケーションを入れて、統一的なことをするとか、いろんなことの活用が可能だと思うんですけれども、そういうような話というのは、文科省のほうからお話があったりとか、あと中教審の中で、そういうふうな検討とか、そういうことに関しては、タブレットに関してどういう考えがあるというふうには、自治体として聞いているんでしょうか。その辺、ちょっと伺いたいんです。
會田 教育総務課長
今お話しの文部科学省の動きといいますか、そこまで統一的なアプリケーションといった動きがあるということは、ちょっと私はそういう動きをつかんでございません。中教審の動き等も、ちゃんとその辺の動きもしっかり確認しながら、行ってまいりたいと思います。世田谷としてのユニークなものも必要だと思いますし、また全国でこのタブレットを配備しているものですから、いいものは取り入れていきたいというふうに考えてございます。
あべ力也 委員
ソフトを世田谷区独自で選定をしたりとか、開発はするというと大変でしょうから、いいものを選定していくということになるんでしょうけれども、いずれしても、ソフトはタブレットに入れれば使えるわけで、いいものは全国的な統一の中でソフトを使うということであれば、そのコストの問題も、スケールメリットから言えば安くなるということもあるでしょうし、そういう文科省の考え方でしょうけれども、そういうものについても、できれば自治体のほうから、文科省であったり、国のほうにそういうコストがかかるような運用ではなくて、全国一律の教育の独立性とか、そういうことを勧奨する話ではなくて、事務的なルーチンのものであったり何かということに関しては、どちらかというと統一していたソフトのほうがいい場合もありますので、そういうことは文科省なんかにも、国のほうに申し入れていくことも私は大事なことだと思うんですけれども、その点はどうでしょうか。
會田 教育総務課長
まず、いろんなところでクラウドサービスということにこだわってきているつもりです。世田谷独自のアプリケーションを一から開発するということを古くから行ってきました。今後、そういうことはなくて、そういうことをやっていると、お金がかかり、独自になって、今、委員お話しがあったようなコストもますますかかっていくという中で、今、ここで全国的な動きのある中で、いいアプリケーションというのは、それだけ大きく伸びていくと思います。各自治体がどんなアプリケーションを選んでいるかというのも、いろんな情報が徐々に入ってきています。そういった中でさらに伸びていくいいアプリケーションを選定したいと思いますし、それは何かといえば、やっぱりクラウドだと思いますので、その辺で考えていきたいと思います。また国に対しても、要望等できる機会がありましたら、それはしてまいりたいと思います。
平塚敬二 委員長
次に、(5)区立図書館運営体制のあり方検討委員会における検討状況について、理事者の説明を願います。
谷澤 中央図書館長
それでは、私からは区立図書館運営体制あり方検討委員会における検討状況について御報告をさせていただきます。
まず、1の主旨でございます。区立図書館運営体制あり方検討委員会を十月二十八日及び十一月二十四日に開催をいたしまして、区立図書館の運営状況に関しまして、民間の評価機関による分析、評価の報告などを踏まえまして、図書館運営の現状と課題、また目指すべき方向性などについて意見交換を行ったところでございます。今後は、これまでの検討委員会で示した資料等を基に、世田谷区にとって望ましい図書館運営体制の方向性について議論してく予定でございます。本日は、現在の検討委員会における検討状況について中間報告をさせていただくものでございます。
続きまして、2の検討委員会の構成でございます。こちらは別紙にあります検討委員会委員一覧のとおりでございます。学識経験者の方四名、そして区民の方四名、そして区職員三名、合計十一名で構成しております。
続きまして、3の検討委員会の主な報告及び検討状況でございます。これまで二回の検討委員会でお示しした資料は、大きく三つございます。
まず、(1)の利用者アンケート等調査分析に関する報告でございます。利用者アンケートにつきましては、例年十一月下旬に平日一日と土曜、日曜いずれか一日の合計二日を使いまして、区立図書館全二十三施設の来館者の方にアンケート用紙をお配りして実施をしております。参考資料1の末尾にアンケート用紙はついておりますので、後ほど御覧いただければと思います。
今回、そのアンケートの結果について、民間の評価機関に分析を依頼をいたしました。その内容が参考資料1となります。こちらの内容については、また後ほど御確認いただければと思いますが、主な分析結果について、かがみ文で三点ほどありますので、ちょっと御説明させていただきます。
まず一点目ですが、世田谷区の人口割合からしますと、四十代、また七十代以上が多くて、利用者も多いんですけれども、十代から三十代は、人口の割合に比べて図書館の利用割合が少なく、そういった若い世代の利用促進が課題となっているというところが一点目の分析でございます。
また、令和元年度の利用者アンケート調査における満足度につきましては、蔵書数、あるいは開館時間、施設の新しさなどに影響を受けているところが見受けられました。総合的な満足度でいいますと、代田、桜丘、鎌田、世田谷の図書館が満足度が高く、また梅丘の満足度がちょっと低いという結果がありましたが、改築をした世田谷、代田における満足度が高いという傾向が出ました。
また、三点目といたしまして、満足度における民間活用館と直営館の比較という点では、開館時間・開館日について、民間活用館で満足度が高いという傾向がありました。梅丘におきましては、業務委託導入初年度、令和元年度ですけれども、そこに効果が表れておりまして、大幅に満足度が上昇しているというような傾向がございました。また、接遇など職員対応については、全館で大きな差はございませんでしたが、民間活用により職員対応の満足度が低下するということはなく、場合によっては上昇するという傾向もございました。
続きまして、二ページ目をおめくりください。二つ目が、(2)区立図書館等施設概要及び行政コスト計算書に関する報告という資料でございます。こちらは参考資料2でございます。A3の横長の資料が二枚ついておりますけれども、こちらは令和元年度が一ページ目、二ページは平成三十年度でありますけれども、区立図書館各館別の基本情報ですとか行政コスト内訳などを記載してございます。
ちょっと資料の構成を簡単に御説明させていただきますと、一番左側の大きく三つ、ブロックが分かれていますけれども、一番上のところに各館の情報ということで、開設年月日ですとか開館時間、蔵書数、貸出し数などを記載してございます。中段辺りに施設別行政コスト内訳ということで、行政コスト合計、人件費相当分合計が網がけのグレーのところで下にまとめてございます。下の行政コスト合計の内訳は、上の水色の部分ですけれども、人件費、間接コスト、物件費、また扶助費・補助費等、減価償却費、維持補修費等の合計でございます。下の人件費相当分合計の内訳は、上から三つ、人件費、物件費のうち賃金、また物件費のうち人件費相当分、これらの合計となっております。一番下のブロックのところに、単位あたりの経費ということで、例えば三つ目の開館一時間あたりの行政コスト、また、その下に貸出一点あたりの行政コストなどを記載してございます。これは貸出し点数などを年間の開館時間で割り返したりしたものでございます。
横に行きまして、上に各館の館名が入っているんですけれども、右側のグレーの網がけの部分、月曜開館で民間活用と書いておりますけれども、梅丘、世田谷、経堂が右側のほうに並んでおりますが、例えばそこの開館一時間あたりの行政コストを見てみますと、大体三万一千円から三万二千円程度になっております。一番右側に平均をまとめております。月曜開館館の平均と月曜閉館館の平均、こちらは直営のものでございますが、やはりそちらの平均と比べますと、ちょっと民間のほうが安くなっているということで、貸出一点あたりの行政コストもそのような状況がございます。
おめくりいただきますと、平成三十年度の表になっておりますけれども、今度は例えば梅丘図書館をちょっと御覧いただきたいんですが、真ん中の月曜閉館の辺りの青い枠で囲っているところがあると思うんですけれども、梅丘図書館でございますが、下のほうに赤枠で囲った人件費相当額、赤枠で囲っていますけれども、こちらが一億千八百万円ほどになっております。
また、ちょっと一ページ目にお戻りいただいて、梅丘は、平成三十年度は直営でございましたけれども、令和元年度は一部委託を導入しております。梅丘図書館、また青枠で囲っている中の一番下、赤枠で囲っている人件費相当分合計、九千百万円ほどになっていますが、差額が大体二千六百万円ほど減ということで、おおむね民間活用している経堂、世田谷、梅丘は全体的に低コストになっているというような傾向がございました。こちらが二つ目のコスト計算書でございます。
そして、かがみ文の(3)にちょっとお戻りいただいて、申し訳ございませんが、三点目が(3)民間評価機関による評価報告ということで、こちらの参考資料3をおつけしていますが、また改めて後ほど御覧いただければと思います。
こちらは、中央図書館及び地域図書館、十五館のヒアリング調査などを基に、基本サービス評価、また事業評価を行いまして、PDCAサイクルが回されているか、その辺の評価を民間評価機関により分析をお願いしました。
主な評価結果のところでございますが、一応評価は大きく二つ、基本サービス評価と事業評価とございます。
まず一点目の基本サービス評価については、基本となる五つの項目、レファレンス業務ですとか組織の運営管理ですとか、五項目についてA、B、Cの評価をいたしました。結果的には、Aの評価については、経堂図書館、また、次いで粕谷図書館が多いというような状況がございました。
そして次に、事業評価につきましては、図書館ビジョンの基本方針が四つございますけれども、その中から地域図書館主体で取り組むべき項目を抽出をいたしまして、こちらもPDCAサイクルのそれぞれステップを段階に分けて評価をいたしました。全体を通じて評価が高かったのは、粕谷図書館、経堂図書館、代田図書館の三館というような状況はございました。これらの結果を受けまして、民間の評価機関から提言をいただいております。
参考資料3ですと、一番最後のページに、五行目から八行目にちょっと記載がございますけれども、三点です。まず一点目が中央図書館の統制機能を強化するための体制や仕組みの整備、二点目は、運営協議会といった外部組織や内部組織による運営体制のモニタリング、そして三点目が事業推進や刷新のための地域館独自の取組の強化について、そういったことについて非常に改善というか、提言をいただいております。
これら今御説明しました三点の資料を提示させていただいて、各委員の皆様からいろいろ御意見をいただきました。そこをまとめたものが、かがみ文、二ページの下のところにあります(4)検討委員会における主な意見ということで、三つに類別をさせていただいております。
まず、①が利用者等のターゲットに関すること、先ほどもちょっとお話しいたしましたが、世田谷区内、若年層、年齢構成の割にしては、その半分ぐらいしか図書館利用をされていないと。区として若年層にもっと図書館に来てもらいたいのか、あるいは今も来ていただいている四十代や七十代以上の方に、これからも引き続き来ていただきたいのか、そういったターゲットをどこに置くかで、蔵書構成やイベントの実施内容など戦略ががらっと変わってくるんじゃないかというような御意見、また三ページをおめくりください。②のコストに関すること、例えばこちらの二点目ですと、コストだけではなくてコストパフォーマンスを向上させるということが重要であって、パフォーマンスを改善するということであれば、人件費を含めたコストもやっぱりかける必要があるだろうと。また、図書館のパフォーマンスは貸出し冊数だけではなくて、例えば滞在時間数とか、そういった視点で見るのも必要じゃないかといった御意見、そして、③の運営体制に関することですけれども、最初の一点目は、第二次世田谷区立図書館ビジョンから、民間活力の活用による運営体制の検討ということで検討していかないといけないんですけれども、サービスの在り方についても引き続き検討していかないといけないといった点ですとか、最後の三点目ですと、中央図書館のガバナンス機能強化を図って、計画をきちっと実行して、その評価を行うといったような管理運営体制を考えていく必要があるという点は、御意見を今のところいただいております。
そして、4今後のスケジュールでございます。令和二年十二月、こちらは十二月二十三日になりますけれども、第三回のあり方検討委員会の実施を予定しております。年が明けて一月に第四回、そして二月には、また、当文教委員会で御報告をさせていただきたいと思います。三月に最後の第五回の検討委員会を開催いたしまして、五月、また最後にこちらの文教委員会で運営体制あり方検討報告、今後の進め方について御報告をさせていただきたいと考えております。
私からの報告は以上でございます。
平塚敬二 委員長
ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
あべ力也 委員
図書館の運営体制の在り方ということで検討されているわけですけれども、公共図書館という性質上、何かを排除するというようなことはなくて、例えば本を借りたい、または研究をしたい、そこで本に関わるいろんなことをしたいという人もいれば、別に本を読まなくても、図書館でちょっとゆっくりしたいなという方もいるわけでありまして、図書館を使うに当たっては、それぞれの例えば区民がこういう方じゃなくちゃ使えないというようなことではありませんので、その辺、敷居の低い施設なわけです。
ただ、例えば夏場はクーラーが効いていて、冬場になると、寒いときには暖房が効いているというような状況なものですから、どうしても全く図書館ということの目的じゃない方も時にはいらっしゃって、私も席でちょっと勉強しているときに、そこで寝ていたり、はっきり言っちゃうと浮浪者の方とかがそこで寝ているとかというようなことがあって、そういう部分に関しては、何かを排除するという施設ではないので、そういう方がいても仕方がないのかなという部分はあるんですが、ただ、利用者のことを考えると、管理者としては、そういう対応というのをどういうふうにするのか、一つ、その問題もあるのかなというふうに思いますけれども、そういう点については、公共図書館を管理する側としては、どういうふうに考えておられるのか、ちょっと伺っておきたいと思います。
谷澤 中央図書館長
今、委員お話しあったような方がいらっしゃる館もございまして、非常に職員が対応に苦慮しているような場合もございます。例えば、皆さんが座るソファで横になって寝ていられたりとかすると、座りたい方も座れませんし、そういった方の場合は注意をさせていただいたりはしていますし、やはりちょっと器物破損みたいなことになれば、当然、警察のほうに相談したりというようなこともございますので、その辺は館と連携しながら対応していっているところでございます。
あべ力也 委員
公共の図書館であるがゆえの難しい運営上の問題もあると思いますけれども、いずれにしても、利用する方が気持ちよく使えるような環境を確保するということは大事なことだと思いますし、また、でも、そういう方でも利用する権利はあるので、その辺のどういうてんびんを考えたらいいのか、大変難しいところで、それぞれ現場の判断になるんだと思います。そういうことも図書館の運営上、どういうふうにしていくのかということを、その図書館の中で働かれる方がどういう対応をしていいのか困るということでは、ほかの利用者の皆さんにもいろいろ迷惑をかけるので、そういった部分に関しては、やっぱりどういう対応をするのかということに関しても、しっかり検討しておいていただいて、マニュアル化しておくことも大事なのかなと思いますので、そういう検討もしていただければなと思います。それは要望しておきます。